
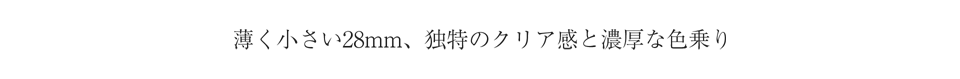
このサイトをご覧の皆様は「いったい何時になったらオールドをやるんだ」と感じているのではないかと。オールドに関しては語り尽くされてきた感があり、有用かつ貴重な情報を提供しているサイトもかなり見受けられる。従ってテクニカルな話題はそちらにお願いするとして、当HPでは作例を中心に、レンズの特長についての簡単なインプレッションと、撮影者による使いこなし方法についてお届けしたいと思う。さて、ライカの28mmといえば「エルマリート」。古い世代となると「ヘクトール」、そして今回取り上げる「ズマロン」が存在する。非常にコンパクトなレンズで、まるでボディキャップのようだが、それとは裏腹な描写で、筆者が非常に気に入っているレンズである。描写特長を簡単にまとめると、まず独特のクリア感のあるレンズで、いわゆるヌケが佳いということとは少し違うのだが、何とも形容しがたいクッキリ・ハッキリな写りである。開放では周辺光量が不足し、かなりドラマチックに周辺が落ちる。このクリア感と周辺落ちが重なった開放の描写に取り憑かれているのだ。また、35mmのズマロン同様、非常に色乗りのよいレンズで、アンダー気味に被写体は3mより以遠、いわゆる、少し「大きな風景」を撮るのに向いているレンズではないだろうか。これから他のレンズを取り上げていく過程でおわかりいただけると思うのだが、ライカのオールドでも、開放の暗いレンズは本当に佳いレンズが多い。このズマロンも例に漏れず、しみじみ「佳いなあ」と感じる1本だ。
(文/編集部K)

開放の周辺落ちはかなりのもので、これだけで画がドラマチックに。開放f5.6では室内で使いづらいが、感度を上げられるデジタルなら少々の暗さでも問題なし。ペットボトルの質感もなかなかのものである。開放からかなりシャープだ。


漁港だから猫が多いのかと思い、聞けば飼っているそうだ。餌を手にすると何処からともなく集まってくる猫たち。
なかなか立体感のある描写だ。みんな大口径レンズの魅力に取り憑かれる。誰だって最初はそうだと思う。しかし、ライカのf3.5あたりから、このズマロンのような開放の暗いレンズは悪い印象を持ったことがない。本当におすすめしたいのだ。

真逆光だと、ほぼ100%に近い確率で、このようなリング状のゴーストが現れる。これを利用して撮るのは、それはそれで面白い。



 ライカ M9-P シルバークローム
ライカ M9-P シルバークローム
世界ではブラックの人気が圧倒的に高いそうですが、日本はシルバークロームの人気も高く、標準でラインアップしてくるあたり、ライカ社が日本のマーケットを如何に重視しているかがよくわかります。その昔家一軒買えると言われ羨望の眼差しを注がれた頃は殆どがシルバークロームフィニッシュ。そのイメージが脈々と引き継がれているのか、確かにライカといえばシルバーの印象が強いのです。
 ライカ M9-P ブラックペイント
ライカ M9-P ブラックペイント
液晶画面にサファイアガラスを用い、軍艦前部のライカロゴ・モデル名が無くなり、軍艦上部にはクラシカルなライカロゴを。そして往年のヴァルカナイト。使い古されたセリフですが、使い込むことでペイントが剥がれ、地である真鍮が顔を出す。まさに自分だけの1台に育て上げるのがブラックペイント・ボディ。
 ライカ M9 スチールグレーペイント
ライカ M9 スチールグレーペイント
角度によってはチタン色に見え、シルバークロームとも趣の違うスチールグレーペイントは、M9とLEICA X1のみに今のところ採用されるカラー。
 ライカ M9 ブラックペイント
ライカ M9 ブラックペイント
カメラとしての基本的な機構はセンサーや画像エンジンをはじめとしてM9-Pと同一。赤丸ロゴ・モデル名が入った方が好みという方に。M9-Pよりリーズナブルなのも嬉しい。
 EPSON R-D1xG
EPSON R-D1xG
世界初デジタルレンジファインダーカメラ、R-D1から数えること3代目にあたるR-D1xG。たかだか600万画素程度・・・と侮ってはならないカメラで、いまでも一級品の画を叩き出します。(ぜひサンプルギャラリーでお確かめください) ライカはちょっと手が届かない、なんて方にも勿論おすすめなのですが、買えば選んでよかったなんてことになるでしょう。

リコー GXR MOUNT A12 [レンズマウントユニット ライカMマウント対応]
ライカレンズをライブビューでパララックス無しで撮る。ローパスレスの画はなかなか渋い色調とともに気に入ると思いますよ。

